News Letter 2025.1.30 第118号

女子高生・車座フォーラム2024
 12月1日(日)に「女子高生・車座フォーラム2024」をオンラインにて開催しました。このフォーラムは男女共同参画推進センター主催で、女子高生に京都大学での学生生活や研究者の仕事を知ってもらうという企画です。
12月1日(日)に「女子高生・車座フォーラム2024」をオンラインにて開催しました。このフォーラムは男女共同参画推進センター主催で、女子高生に京都大学での学生生活や研究者の仕事を知ってもらうという企画です。
今年で19回目の開催となり、高校生64名、保護者9名の参加がありました。
はじめに稲垣 恭子センター長より挨拶があり、続いて「京都大学ここのえ会」(京都大学の男女共同参画推進事業や女子学生、女性研究者等へ緩やかな支援を行う同窓会)の羽生 祥子氏よりビデオメッセージがありました。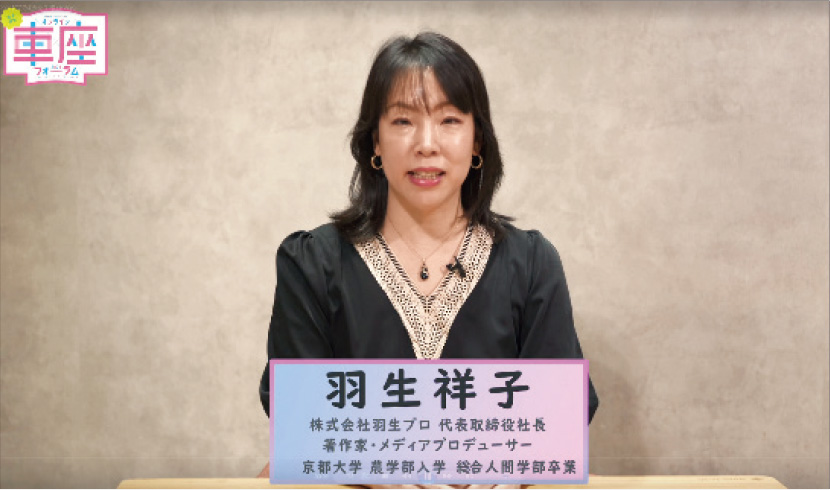 羽生氏ご自身についての高校時代の受験体験から京都大学での学生生活、現在にいたる就職など大変興味深いお話を語っていただきました。
羽生氏ご自身についての高校時代の受験体験から京都大学での学生生活、現在にいたる就職など大変興味深いお話を語っていただきました。
続いて、前半のグループワークは各学部に分かれて行い、始めは緊張気味だった女子高生も、学部での学びや大学生活について教員や京大生にじっくりと話を聞くことができ、和気あいあいと盛り上がりました。
後半のグループワークでは、文系(文学部・教育学部・法学部・経済学部・総合人間学部(文系))、理系(理学部・医学部(医学)・薬学部・工学部・農学部・総合人間学部(理系))と大きく2つに分け、合同でのグループワークを行いました。それぞれの学部の教員や京大生が学部の特徴などについて説明し、参加者からは自身の興味があることについて学ぶにはどの学部に入ればよいのか、事前に調べていて疑問に思ったことなど、様々な質問があり、学部を横断するような質問に複数の学部から返答をすることが出来ました。 保護者においては、ウェビナー形式での開催で京大生と理学部、工学部の教員が質問に答えました。受験生を持つ保護者ならではの視点からチャット機能を用いてたくさんの質問がなされました。
保護者においては、ウェビナー形式での開催で京大生と理学部、工学部の教員が質問に答えました。受験生を持つ保護者ならではの視点からチャット機能を用いてたくさんの質問がなされました。
今回も各グループワークにおいて、京都大学の学生や研究者を知っていただく有意義な時間となり、盛会のうちに終えることができました。
今年度のアンケートや車座フォーラムについてはHPに掲載していますのでご覧ください。
https://www.cwr.kyoto-u.ac.jp/rooting/kurumaza/
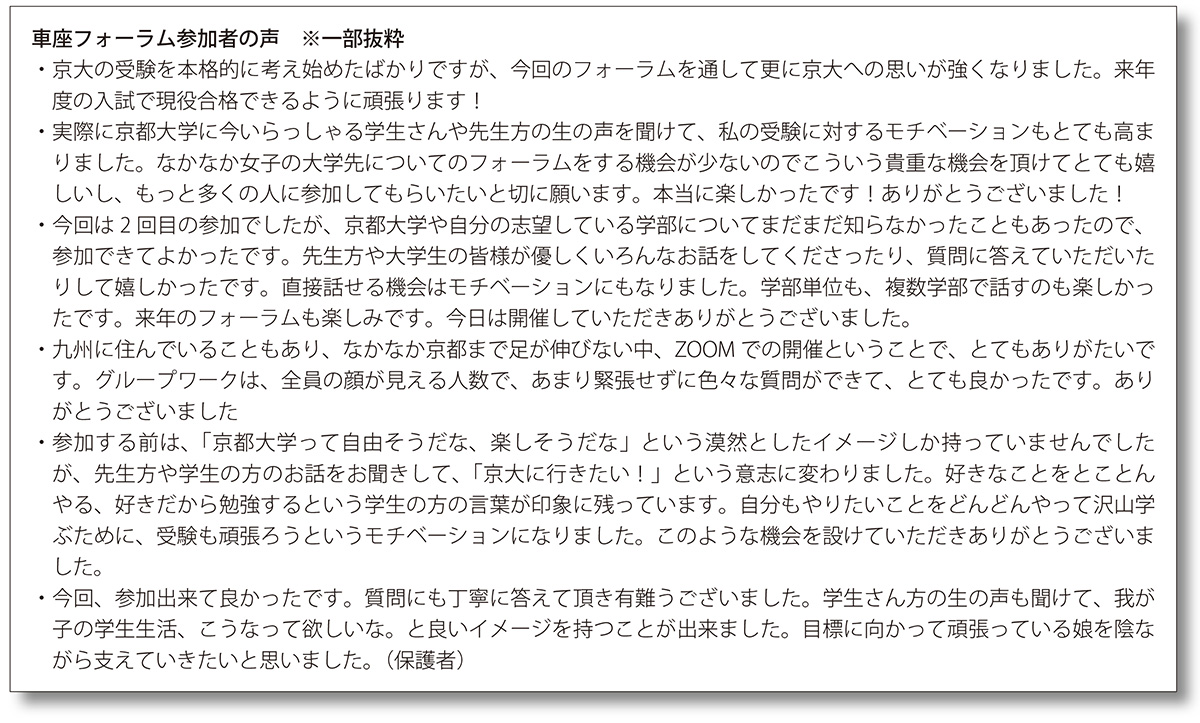
京都大学・国際連合大学共催シンポジウム「世界の中のジェンダー」開催
本学と国際連合大学との共催で、2024年12月2日に、「世界の中のジェンダー」をテーマに、芝蘭会館山内ホールおよびオンラインにてシンポジウムを開催しました。本シンポジウムは、グローバルな視点からジェンダー平等について議論を深め、国際的な枠組みの中での日本の大学や学問研究の今後の展望を考える場として実施したもので、 会場に約70名、オンラインに約130名が参加しました。
会場に約70名、オンラインに約130名が参加しました。
まず、稲垣 恭子 理事・副学長による開会の挨拶から始まり、続いて白波瀬 佐和子 国際連合大学上級副学長・国際連合事務次長補が基調講演を行いました。講演では、ジェンダー平等の重要性について、社会における女性の役割、女性が社会で働く際の現状と課題、さらに研究者としての視点など、幅広いテーマが取り上げられました。白波瀬 上級副学長のグローバルな視点に基づく講演は、参加者に深い感銘を与えるものでした。 その後のパネルディスカッションでは、モデレーターを務めた蓮尾 昌裕理事補を中心に、白波瀬 上級副学長、伊藤 公雄 名誉教授(京都大学・大阪大学)、木下 彩栄 理事補が多岐にわたる議論が展開されました。認知症を含む医療の課題や、ジェンダー平等の観点から見た日本社会の現状と未来などについて意見が交わされ、参加者も熱心に耳を傾けていました。
その後のパネルディスカッションでは、モデレーターを務めた蓮尾 昌裕理事補を中心に、白波瀬 上級副学長、伊藤 公雄 名誉教授(京都大学・大阪大学)、木下 彩栄 理事補が多岐にわたる議論が展開されました。認知症を含む医療の課題や、ジェンダー平等の観点から見た日本社会の現状と未来などについて意見が交わされ、参加者も熱心に耳を傾けていました。 参加者からは、「大変参考になるシンポジウムだった」、「講演とディスカッションによって気づきを得た」といった感想が多数寄せられ、参加者に新たな視点や学びを提供し、ジェンダーをめぐる課題をより深く考える機会となりました。
参加者からは、「大変参考になるシンポジウムだった」、「講演とディスカッションによって気づきを得た」といった感想が多数寄せられ、参加者に新たな視点や学びを提供し、ジェンダーをめぐる課題をより深く考える機会となりました。
KuSuKu クリスマス会(親子イベント)を開催しました
 学童保育所 京都大学キッズコミュニティKuSuKu(クスク)では、2024 年12月22 日(日)に、「KuSuKu クリスマス会(親子イベント)」を開催しました。
学童保育所 京都大学キッズコミュニティKuSuKu(クスク)では、2024 年12月22 日(日)に、「KuSuKu クリスマス会(親子イベント)」を開催しました。
午前は、ギターの伴奏で子どもたちが好きな楽器で演奏したり歌を歌ったりした後、オーケストラ奏者を招いて、弦楽四重奏によるクリスマスソングメドレーを聴きました。
いつも子どもたちが遊ぶ遊戯室がまるでコンサート会場のように、弦楽器のハーモニーが優しく響き渡り、大人も子どももしばしじっと耳を傾けていました。その後、子どもたちがタクトを振って、オーケストラの指揮者になった気分を味わいました。
午後は、サプライズでサンタさんがたくさんのプレゼントをもってKuSuKuに来てくれました。子どもたち一人一人にプレゼントを渡した後、素敵な景品の獲得を目指してビンゴ大会が行われました。会場となったミニホールでは「リーチ!」「ビンゴ!」といった子どもたちの歓声があがり大盛り上がりのイベントになりました。
その後、子ども向けにはバルーンアートづくり、保護者向けには、KuSuKuの開所準備や開所から1年間の活動を写真や動画で振り返る報告会を行いました。最後に親子全員でケーキを食べて、一足早い、クリスマス気分を満喫できた親子イベントになりました。
令和7年度 保育園入園待機乳児保育室「ゆりかご」
2月3日より申込受付開始・一時保育対象者の年齢緩和のお知らせ
学生及び研究等に携わる教職員の研究と育児の両立を支援することを目的とし、男女共同参画推進センター内に「保育園入園待機乳児のための保育施設」(愛称ゆりかご)を設けています。この保育施設は、自治体に保育園入園申請をおこなったが、入園待ちを余儀なくされている研究者等を対象としています。
【ゆりかご】 令和7年度は4月2日(水)から開室の予定で、利用申込の受付を2月3日(月)より開始します。利用希望の方は下記の要項を熟読のうえ、お申込みください。
令和7年度は4月2日(水)から開室の予定で、利用申込の受付を2月3日(月)より開始します。利用希望の方は下記の要項を熟読のうえ、お申込みください。
https://www.cwr.kyoto-u.ac.jp/support/care/nursery/
【ゆりかご(一時保育)】
入園待ちではないが、緊急に保育が必要な状況である乳児を対象に一時的に保育をしています。
利用資格については「ゆりかご」に準じています。
2024年12月24日より、小学校就学前の幼児の一時保育も開始しました。
詳しくは下記をご覧ください。
https://www.cwr.kyoto-u.ac.jp/support/care/temporary/way/
学生・研究者・卒業生紹介サイト「MY STORY」更新しました!
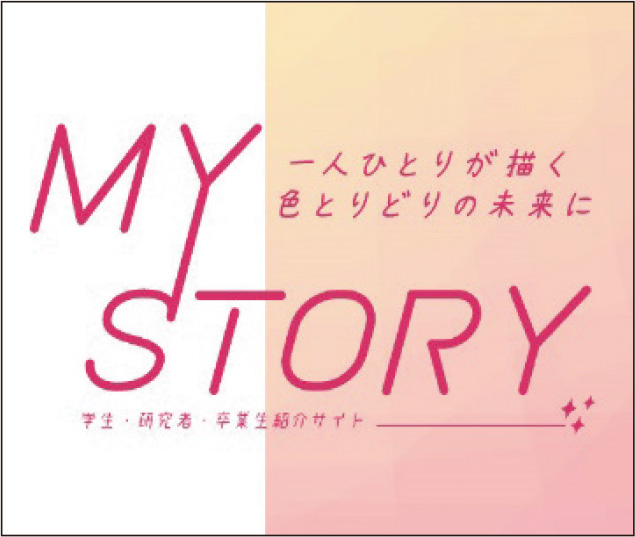 研究者や京都大学を卒業し社会へ出て活躍している先輩たちから、現在の仕事について、大学時代の勉強と生活、そして高校時代どう過ごしていたかなどのお話、在学生については留学体験記を掲載しています。
研究者や京都大学を卒業し社会へ出て活躍している先輩たちから、現在の仕事について、大学時代の勉強と生活、そして高校時代どう過ごしていたかなどのお話、在学生については留学体験記を掲載しています。
「MY STORY」是非ご覧ください。
https://www.cwr.kyoto-u.ac.jp/mystory/

連載: 研究者になる! -第99回-
工学研究科 助教 良永 裕佳子
右手と左手は鏡写しの関係です。右手の鏡像は左手ですが、実物の両手が同じ形で重なりあうことはありません。このように物体とその鏡像とが重ならない性質を「キラリティ」といいます。このキラリティをもつ分子、キラル分子が私の研究対象です。
キラリティは化学にとどまらない普遍的な概念です。分子よりもさらに小さな素粒子、鉱物の構造や銀河にいたるまで、さまざまなものに現れます。小さなキラリティが積み重なって、目に見えるキラリティになる。大学時代に出会ってからいまなお、不思議にあふれたキラリティへの興味はつきません。
あまのじゃくな気持ちから理系に転向
中3の文理選択の時期が迫るまで、将来は文系学部に進むものだと疑いもしませんでした。でも、思春期ゆえか、経済学者の父への反抗心からか、あまのじゃくな気持ちが生まれて、理系コースを選択すると決めたんです。想定外の選択だったので、勉強は苦労しました。とくに、抽象的な世界の中で物事を考える数学には当時、苦手意識がつのるいっぽうでした。そんななか、化学は化学式や構造などの目に見えるものから考えられる科目。「これならわかる」と直感したのです。
大学院修了後も研究をつづけたくて、大学に残る道と、企業の研究施設で勤める道の両方を視野に入れて就職活動をしました。大手化学メーカーに入社して2年半後、企業での研究のおもしろみを味わいはじめた矢先でしたが、巡ってきたタイミングとチャンスに飛び乗って、京大に着任。アカデミアの研究者としての挑戦をはじめました。
いま思えば、直感的に物事を捉えることからはじまる私の研究スタイルは、企業よりも学術研究の世界に向いていたのかもしれません。企業の研究はとても計画的で、数年後の成果を見据えて確実に成果を重ねながら、研究します。いっぽうの私は、「これ、おもしろそう!」というふんわりとした興味や、「これはうまくゆきそうだ」という根
拠のない手ごたえが原動力。すぐに社会に役だつ研究ではないかもしれませんが、純粋な好奇心を基盤に研究ができれば、もっと充実した研究生活になるはずだという予感もありました。
着任からことしで2年。研究は走り出したばかりです。まずはキラル分子を軸に、新分子をつくりだしたり、その性質を調べて理解したりしながら、新しい領域を切り拓きたい。そして、「ここが私の場所です」と胸を張れるようになりたい。その思いで、分子と向き合っています。
自分らしさは変わりつづけるもの
進路選択には「自分らしさ」を見つけることが大切だといわれますが、自分らしさは変わるものだというのが私の持論。若いうちはとくにそうではないでしょうか。そんな私も、まだまだ「自分らしさ」は模索中。これまでの選択で頼りにしたのは直感です。誤った選択もあったかもしれませんが、将来、ふり返って過去の自分を眺めたとき、「あのとき私は、ああ考えていたからあの選択をしたんだった」と、自分のなかで理屈がとおっていれば後悔はしないだろうと思っているんです。
「化学が好きかも」という直感で進学を決めた京大工学部。化学分野一つをとっても、研究テーマは宇宙から微生物にいたるまで、身近な衣食住から極限環境の自然まで、あらゆるスケールの事象を研究しています。アプローチの切り口も多種多様。「おもしろそう」と感じたら、飛び込んでみてください。自分の興味や関心のアンテナに引っかかるテーマにかならず出会えるはずです。

