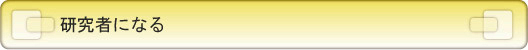落合恵美子( 文学研究科・教授 )

出産・育児はマイナス要素か
修士論文提出を半年後に控えた夏、妊娠したことを知った。困った、と思わなかったわけではないが、これは乗り切れる、と考えた。人生の中でいつも「産める」とは限らない。自分が用意できていないときもあるだろうし、周囲の状況が許さないときもあるだろう。困難ではあってもなんとか「産める」ときに授かるとは、なんと幸福なことか。わたしはすぐに産むと決めた。
大胆にもそう考えたのには訳がある。それまでの数年間は、わたしのこれまでの人生で最も惨めな数年間だった。大学院に入ったものの、もやもやとした問題関心にどこから道をつけたらよいか分からず、無為に2年間が過ぎてしまった。そこへ父と祖母の病気。介護する母を手伝いながら、気持ちは落ち着かなかった。そこで、あろうことか、結婚。彼の関西での就職を機に、結婚か別離かを選択せざるをえなくなったのだ。大学院を続けるのかどうかも決断を迫られた。男ごときのために学業を途中で投げ出しそうな娘に両親は失望を隠さず、研究室の仲間は去り行く者を見るような目で見た。耐え切れず、わたしはフェミニストセラピーのお世話になった。何度目かに思い当たったことがあって、涙が溢れ、帰りの山の手線の中でも涙が止まらなかったことを覚えている。
結局、わたしが選んだのは、彼と結婚して京都についていく、しかし大学院はやめずに東京に遠距離通学する、という超中途半端な解決だった。しかし、開き直って言わせてもらえば、「中途半端」以外にどんな解決があっただろう。相手に合わせながら自分も通すためには。女の懸命な選択は、傍目にはしばしば中途半端に見えてしまう。
新婚の6ヶ月は真っ暗な気持ちで送った。「行」のように本を読み、疲れると新聞の求人欄に目を走らせた。タウン誌のライターにでもなれたら、ものを書くことは続けられるだろうか、などと考えながら。しかしそのうち落ち着いてきて、修士論文の構想もおぼろげながら見えてきた。なんとか立ち直れたのは、「僕が支えられるうちに体勢を立て直したらいいよ。でもずっとは支えられないからね。」と言ってくれた夫、京都に来てから出会った女性学研究会の仲間たちのおかげだったと心から感謝している。同じ方向を模索している同輩研究者のネットワークは、研究を進めるためになくてはならないものである。
さてそうして修論執筆を始めたところで妊娠発覚。1年前ならとても産めなかったと思うと、産むという決断のできる自分が嬉しかった。妊娠5ヶ月で修論提出。せり出したお腹を妊婦用の特製吊りズボンに包んで口頭試問を受けた。「生まれちゃったらどうしようかと思って、厳しい質問をするときはビクビクだったよ」と後から指導教官に聞いた。
育児と研究の両立は大変でしょう、と人は言うけれど、わたしは必ずしもそうは思っていない。大変なのは、研究そのもの。いい着想が得られなければ、子どもがいようがいまいが研究はうまくいかない。実を言うと、着想という点では、子育て真っ最中の女性は好条件にあるのではないかという仮説をわたしはひそかに抱いている。妊娠して授乳してたくさんのホルモンが身体中を駆け巡っているとき、毎日が新鮮な経験で埋め尽くされているとき、柔軟になった頭と心が普段は思いもかけない斬新な発想を生み出すというのはありそうなこと。実際、わたしも産休明けに最初に書いた論文がその後の研究の方向を決めることになった。比べるのはおこがましいけれども、ヘレン・クイーン前アメリカ物理学会会長も、京都大学での講演会で、ひとり子どもを産んではひとつ大きな発見をしたとおっしゃっていた。出産や育児を研究に対するマイナス要素としてばかり見るのはやめたほうがいい。
しかし、育児がマイナス要素として作用することも、たしかにある。子どもが小学生だった頃、ある大規模プロジェクトに関わっていた。古文書を解読してデータベース化して統計分析するという理系のようなプロジェクトで、大部屋で大勢の研究者が朝8時半から夜8時か9時、ときには深夜まで一緒に作業をしていた。同僚の研究者は男性も女性も単身赴任が多く、子どものいる女性はわたしだけだった。昼間は入力作業が忙しいため、5時や6時からリサーチミーティングが入るのはざらで、そわそわするわたしに同僚の単身女性が「落合さんは帰っていいよ。わたしが落合さんの分も頑張っておくから」と親切心で言ってくれたものだ。しかし、翌朝来てみると、わたしの考えとは違う方針が決まっている。やはり帰れない。他の人たちが頑張っている間は。育児をマイナス要素にしてしまう大きな要因は職場環境なのだけれど、何がつらいのか、どうしてくれたら助かるのか、立場の違う同僚に分かってもらうのが一番の課題だろう。
最後に、ポジティブアクションについて触れておきたい。わたしはこれまで研究者へのポジティブアクションの適用には後ろ向きだった。実力本位という職種の性格となじまず、女性研究者の評価をかえって落とすと考えたからだ。社会学などの領域ではもはや実力勝負で十分という理由もある。しかし近頃、「有力」な男性研究者たちと話していて、(少なくとも文系では)重要と考えるテーマや視角に男女差があるということを痛感する場面があった。しかも男性たちは、女性が重要だと考える問題を軽視したり特殊だとみなしたりする傾向をいまだに持ち続けている。つまり「実力」の測り方には性別による違いがある。選ばれる側の性比をあらかじめ決める必要はないけれど、選ぶ側の性比をむしろ問題にすべきではないかと思うようになった。