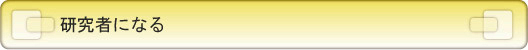石井 美保(人文科学研究所・准教授)

さよならイキイキ・モデル
女性研究者への応援冊子ともいうべき『たちばな』という媒体に、「研究者になる!」という連載タイトル。この条件での執筆となると、何とはなしに、「研究も家事も育児も、大変だけど毎日充実しています!」という、ポジティヴでエネルギッシュな文章を書かなくてはならないような気がしてくる。こうした模範的なイメージを、ここでは仮に「イキイキ・モデル」と名づけたい。仕事と家庭生活を両立し、イキイキと輝いている女性研究者像である。
でも待てよ、と思いとどまる。この冊子の主な読者層が若手の女性研究者だとしたら、そうしたモデルを提示されるのは、ちょっと息苦しくなることではないか。ちょうど、「女性が輝く日本!」といった上からの掛け声に、息苦しさを感じるのと同じように。切れ目のないキャリア、自己点検・評価、論文執筆に学会発表。家事に育児に介護。私たちの周りはすでに、身動きのできないほどの「マスト」項目で埋まっている。この小さなエッセイの中でまで、イキイキ・モデルを奨励しなくてもよいだろう、と思うことにする。
私の専門は文化人類学である。女性研究者のおかれる状況は、理系か文系かによって随分変わってくると思うが、文系の中でも文化人類学は、長期のフィールドワークが必須という点で特殊だといえる。大抵の学生は、博士課程在籍時に一年ほどの現地調査を経験する。私の場合、2000年前後に通算15ヶ月間ほど、ガーナの農村で調査を行った。研究テーマは精霊祭祀や呪術といった地域の在来宗教と、多民族社会における人々の関係性である。精霊を祀る司祭の家に居候させてもらい、宗教実践に関する調査を進める傍ら、村人の生活を知るために農地や森の中を歩き回った。
大学院博士課程といえば、年の頃は26歳前後。同年輩の友人知人はそろそろ結婚していくお年頃である。電気や水道のない村で、ときにスコールに叩かれ、マラリヤ熱に罹りつつ、呪術や儀礼について学び続ける日々。そんな私の元に、「私たち結婚しました!」という、幸せいっぱいの写真付きハガキ(日本から転送されてきた)が何枚となく舞い込んでくる。これはなかなか、シュールといおうか、哀愁を誘うといおうか、「私って一体…」という気持ちになる経験である。
そんな私もどうにか博士論文を提出し、学振PDの身分でアムステルダム大学に留学することになった。ここで私にとっての大問題は、留学期間が妊娠・出産時期とまるきり重なってしまったことである。おまけに、やはり人類学者である夫も同時期にインド留学が決まってしまった。仕方がないので、夫にはインドとオランダを往復してもらうことにして、オランダで出産してみることにした。結果としては、留学というよりも「産みに行った」というほうが相応しいオランダ滞在ではあったが、その中でも印象深い出会いはあった。アムステルダム大でポスドクをしていたマリーンは、私と同じくガーナ研究者。まだ1歳に満たない娘を研究会に連れてきて、ガーナ人の旦那さんと交替であやしていた。当時40歳にして既に著名な研究者であったビルギットは、9歳の息子の母であり、持病を抱えながらの研究生活。息子の誕生日に大掛かりなパーティを催したことを嬉しそうに話した後、ほっと息をついて、「でも大変よ」と呟いていた。おそらくは妊婦の身だったからこそ、研究という枠組みを離れて何か通じ合えたように感じた瞬間を、今もときどき思い出す。
オランダで長女を出産し、その6年後に日本で次女を出産。この十年ほど、二人の娘を調査地に連れていく「子連れフィールドワーク」を敢行中である。というと、調査地でも仕事と育児をこなす超イキイキ・ライフを実践しているようであるが、そうではない。何かと抜けている母を心配する子らに「ついてきてもらっている」というのが実情である。こんな風に、ときにジタバタ、ときにヨロヨロと過ごしているうちに、定年を迎えることになるのだろうか。いずれにしても私にとって、「キャリアも家庭も!」という無限のループからしばし逃れて、何者でもない自分のあり方を見直せるのは、やはりフィールドにいるときなのかもしれない。