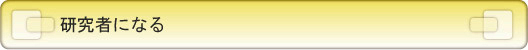田口真奈(高等教育研究開発推進センター ・准教授)

自分なりの研究者像を模索しながら
ついに、このコーナーの執筆依頼が回ってきたことを、第一回目の執筆者であった同僚教授に伝えると、「田口さんなんか、ネタ満載でいくらでも書くことあるでしょ!」と言われた。そうかもしれないけれど、さて、何を書けばいいのやら。後輩女性研究者が一番目を輝かせて食いついてくるのは「結婚ネタ」なのだが、ここでは文字通り「研究者になる」までについて書いてみようと思う。
強い意志をもって研究者になったわけではないが、「働く」ということについては、強い意志をもっていた。もっと正確にいうと、私はずっと、「働くお母さん」になりたかった。今は亡き母がそうであったからだと思う。もっとも、大学生の時には、「働く」ことも「お母さんになる」こともこんなに大変だとは思ってもみなかった。まず、お母さんになるためには、「この人となら」と思う人を見つけ、子を授からなければならない。両方とも、自分の努力だけでなんとかなるものではない。また、職を選ばないのであれば「働き始める」ことは比較的たやすいが、「働き続ける」ことはとても難しい。これもまた、特に子どもができてからは、自分の能力や頑張りというより、条件が整うかどうかによるところが大きい。私が現在、6歳の娘、1歳の息子をもち、会社員の夫と同居し、理解ある義母や保育園や隣人に支えられて、尊敬できる同僚とともに教育研究に邁進させていただけているのは、ひとえに運がいいからである。
就活の時期を迎えて、「働くお母さん」になるためには「子どもがいるというハンディをもっていても欲しい人材になっていないとダメなんだ」と強く思い、そのときに「これと誇れるもの」をもっていない自分に気づいて大学院への進学を決めた。ただ、当時所属していた大阪大学教育技術学講座の研究室には、学会長をはじめとする、立派な研究者がたくさんおられたので、自分が「研究者」になれるとは到底思っていなかった。だから、修士課程在籍中に、資格をとった。所属学部で取れたのは、中学校と高校の教員免許。小さい子が好きだったから、幼稚園教諭の免許をとりたかったが、自分の大学ではとれなかった。そこで学科試験と実技に合格すればとれる保育士の資格をとった。
修士課程に進み、講座のプロジェクトに参加させていただき、学会デビューをすると、視野が研究室の外にも広がった。学部時代には初等中等教育の授業研究をしてきたが、研究の蓄積があまりない(ように当時見えた)幼児教育に携わることは、やりがいがあることのように感じて、保育士の資格をもってアルバイトも始めた。「現場」に入れば、「これだ!」と思える幼児教育に関する研究テーマがみつかるかも、との甘い期待があったのだが、オムツを替えているうちに終わってしまった。大阪大学には幼児教育を専門にしている講座がなかったために、大阪教育大学の先生のゼミに通わせていただいたりもしたが、いいテーマをみつけることができず、結局、修士論文のテーマとしたことをそのまま博士論文でも追究することにした。
当時は、初等中等教育におけるメディア教育を研究対象とする研究室にいたが、私はその中で「映像視聴能力」をテーマにしていた。博士論文執筆の過程で、単に「テレビ番組の理解」ということを越えて、人が「見てわかる」とはどういうことなのかを知りたいと思ったが、その関係領域の広さに、茫然とした。と同時に、「これが研究か」と面白さも知った。「今の自分では扱いきれない」ことを素直に認め、「範囲を絞る」ことも学んだ。また、狭い領域ながら「自分が日本で一番詳しいのかも」と思えることができたことは(それがほんのささいな領域であっても)、自信にもなった。
博士号取得の過程もネタ満載だったのだが、紙幅の都合上カット。
ともかく、無事博士号を取得した。が、取得しても就職はない。たまたま知り合いが訪問するというのに便乗して訪ねたゼミが、今いる職場の前身であった。そこで「大学教育」が研究領域になることを知った。研究の蓄積がないのは幼児教育以上。これは面白いと思った。研修員やら、関東での就職やら、ハーバード大学での在外研究やらを経て、現在に至る。
助教時代に再会した高校の同級生が、「自分の研究は、うまくいけば、生物の教科書の記述がちょっと変わるかなっていう研究」と教えてくれたことがあった。率直に「すごいな」と思い、そういった領域に憧れをもった。同時に、不公平だな、とも思った。なぜなら、そのとき、私はすでに職を得て、科研費もいただいていたのに対して、友達は不安定な身分のままだったからである。そのときに、思った。私はノーベル賞をとるような研究者にはならないけれど、そういう人材も育つような環境づくりに貢献できたらと。それはそれで必要ではないか、と。いろいろな研究者がいて、いろいろな領域がある。私は、運命が導いたこの場所で、できることを精一杯やろうと思っている。