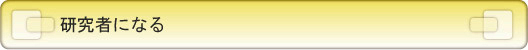氣多雅子(文学研究科・教授)

生活費を稼ぐということ
いま教師の立場で、これから研究者になろうとする院生たちと向かい合っていると、彼らは私たちの頃よりずっと大きな不安を抱えているように見える。その不安にはいろいろな要素があるが、いちばん大きな要素はやはり就職についての不安であろう。文系では理系以上に研究者としての職を得ることは困難であり、院生たちは研究実績を積むことを急かされ、先の見えない就職戦線に追い立てられている。
しかし、大学での女性の就職に関していえば、私たちが院生であった頃より、現在の方がはるかに恵まれていると言ってよいであろう。三〇年前には、特に哲学・思想の分野で女性が就職するというのは特別な僥倖によらなければ不可能であると一般に思われていた。私も就職活動には連戦連敗で、担当者から「女性は採らない」とはっきりと断られたこともある。だから、最初から私には研究をすることと生活費を稼ぐこととは別に考えなければならないという思いがあったが、そのことに悩んで消耗することはなかった。それは、生活費を稼ぐということそれ自体の意義に私が迷いをもたなかったからである。思い返してみると、そのことの意義を決定的に私に刷り込んだのは、中学一年のときに読んだロマン・ロランの『魅せられたる魂』であった。
この小説のヒロイン、アンネットは若くして父親の遺産を失い、生涯果てしない職探し競争に明け暮れることになる。彼女がどういう態度でそれに立ち向かったかは、次の一節に象徴的に示されている。第一次大戦後に破産した旧い友人が新聞社のタイピストとなって、屈辱的な経験をして逃げ出してきたことをアンネットに訴えると、彼女はこう答える。
「じゃ、その地位は空いているのね、今は?」
相手はびっくりしてしゃっくりが止った。
「まさかそれをお取りになるんじゃないでしょう?」
「どうしていけないの? 貴女の口からパンを奪るのでなかったら」
「わたしはもうあのパンは食べないわ」
「わたしはもっといろんなパンを食べたのですよ!パン屋の手はあまり近くから見ない方がいいってことはわかってるのよ」
「わたしは見たんですもの。もう食べられないわ」
「わたしは見るわ、そして食べるわ」
狂ったような相手は、頭の中は憑かれていたにも拘らず、アンネットの顔を眺め、顎で挑戦している相手の上機嫌をみて笑わずにはいられなかった。
「食慾がおありなのね!」
「でも仕方がないわ」
とアンネットは言った。
「わたしは精神だけで生きてるんじゃないんですもの。先ず食べるのですわ。精神は後廻しにしたって何も損にはならないでしょう。わたし保証しますわ、でたらめではないんですよ」
(中略)彼女はその日の午後、夕方を待たずして、まだ温味の残ったその席をとってしまった。
[『ロマン・ロラン全集7』みすず書房、1980年、368頁以下]
誤解のないように言うと、ここから私が受け取ったのは、食べることがすべてに優先するということではなく、食べることへの敬意と食べることの誇りである。生活費を稼ぐということを単なる金儲けと区別するのは、この敬意と誇りであろう。もっともこの誇りは罪と表裏一体であり、それ自体が罪を引き受けることの確認でもある。ちなみに、シモーヌ・ヴェイユは単純作業の工場労働者の境遇を奴隷的と見なしたが、境遇の惨めさとは別に、すべての労働を支える食べることの誇りを、ヴェイユは見逃しているように思われる。私は結局、大学に職を得ることができたが、生活費を稼ぐことが生きることの基本であり、生活費を稼ぐことにおけるどのような屈辱も生活者の矜持を傷つけることができないということは、大学という職場でも変わらないと知ったのである。