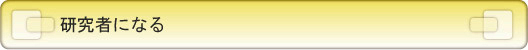稲垣恭子(教育学研究科・教授)

試行錯誤の連続
「研究者になる!」というタイトルで何かを書くのはちょっと居心地が悪い。そんなに明確な見通しをもって「選択」したわけではなかったし、その後の過程もあちこちに頭をぶつけながらの試行錯誤の連続だったなあと思うからである。ただ、外から、たどったコースだけみると、学部からずっと同じ分野を専攻し、大学に職を得て現在まできているという一本道である。脇目もふらず邁進したといえたらいいのだが、実際はむしろ迷いつつ手探りできたというしかない。
教育学部に入ったけれど、「教育」への期待よりも漠然とした不信感を感じることが多かったわたしが、結局ずっとそれとつき合うことになったのも思えば不思議である。教育にあまり前向きではなかったこともあったのか、たまたま出会った「教育の逆機能」とか「意図せざる結果」というキーワードに親近感を覚え、だんだんと教育や社会生活一般についての違和感を社会学的に解くことに興味をもつようになった。そのうち、「教育」そのものを研究するというよりも「教育で」考えるというスタンスもありなんだと気づいて面白くなった。
そんなことで急に進学することに決めたので周囲も驚いたが、入ってから専攻した教育社会学では博士課程まで進学した女子学生はこれまでいないと知って、わたしのほうも驚いた。その1978年頃には大学院への進学も身近な進路になりつつあったが、まだ職業キャリアとしてライフコースが描けるほど制度化されていたわけではなかった。女子に限ったことではないが、先行きは不透明だった。大学院もいわゆる「学問共同体」的な場から、制度化されたキャリア形成の場へと移行する過渡的な時期だったようにおもう。そんななかで、モデルもなく無手勝流の勉強でいつも不安だったが、自由さもあった。
研究会や共同研究での議論も、成果とは別に共通の基盤の確認と新しいアイデアの発見の場にもなっていたように思う。共同研究はまとまらないことも多いが、大学院の間に研究室ではじめて行った共同研究も経験した。全体の枠組みより自分の仮説やストーリーにこだわって長時間議論して疲れることもしばしばだったが、自分にはないような切り口に出会ってはっと思いつくことも少なくなかった。もうひとつ、決まったテーマの下での共同研究やプロジェクトとしてではなく、新しいテーマを発掘して、十分に練れていなくても大胆な仮説を紹介し合うという気楽な研究会を長く続けていたが、それも「教育」という規範的な現象に対する社会学的リアリティの感覚を磨く場になったのではないかとおもう。研究のインセンティブは「現実」に対する違和感を生活とは別次元の方法で埋めたいという衝動によるところが大きいと思う。教育社会学がその方法としてわたしに合っていたのか、やっているうちに合ってきたのかわからないが、だんだんと思考法が身についてきたように思う。
研究では、これまで主に校風や生徒のサブカルチャーなど学校に独特の文化について、それが形成される相互行為に焦点づけた研究から出発して、最近はより歴史社会学的な方向に関心が広がってきている。とくに最近の関心は、「たしなみ」「師弟関係」「女性の教養」など、近代教育の前提のなかでは正面からあまり取り上げられてこなかった教育の側面を歴史社会学的な視点から掬いあげてみたいということにある。資料を読んでいるのは愉しいが、日常の感覚から遠くなったこれらの対象をどうやって「現在の歴史社会学」にしていけるのか、試行錯誤しながら取り組んでいる。