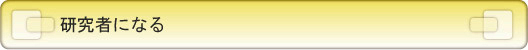山田 文(法学研究科・教授 )

研究は楽しくやろう
学部生時代は、サークル活動(模擬裁判)に明け暮れ、授業のノートは友人(の友人)から借りて一夜漬けで試験を受けるという絵に描いたようなお気楽な日々を送っていました。在学したのは東北大学ですが、これも、当時の実家から徒歩5分で行ける国立大学で、かつ、女子でも就職率の良さそうな学部を選んだという大変消極的な理由です。周囲が司法試験の勉強をしていても、あまり興味もなく、むしろ経済的自立なければ自由なしという信念が強かったので、とにかく早く就職しようと思っていました。そんなわけで、4年生の夏には就職活動も終了し、あとは複数あった内定の間で迷っているという状況でした。
ところが、その秋、当時(これもかなり打算的な理由で)入っていた民事訴訟法のゼミの報告準備で、初めて、自力で資料・文献を芋づる式に探りつつ、「習う」のではなく自分で「探検する」困難と面白さを知りました。問題設定を軽くしておけばそこまで、複雑にしていけばどこまでも深く潜っていける、これまでと違う世界を発見できるという研究のもつスリルと達成感に、遅ればせながらようやく気づいたわけです。そしてタイミング良く、教授に助手に誘われるという幸運に恵まれました。あくまで打算的な私は、大学院の門の狭さ、授業料負担、就職の不安定さを考えて修士課程は考えていなかったのですが、給料をもらえるなら大学に残ろうと極めて楽観的な決断をしてしまったのです。
研究職を考えていなかったからこその怖いもの知らずで飛び込んだのはよいものの、その後になって、学部時代の不勉強もあり、研究者としての資質・方向性に大変悩むことになりました。助手論文のテーマとして「裁判外紛争解決手続」(ADRと呼ばれています)という、調停や仲裁といった判決以外の手続を選択するまでも長かったのですが、その後も、新しい分野だったこともあり、伝統的な法理論との関係を含めて、議論の手掛かりをつかむまでは真っ暗闇を歩くようでした。逃げ出したいと思ったことも一度ならずあり、体調を崩して入院騒ぎということもありました。しかし、法的解決のための手続では、本当は主役であるはずの当事者が萎縮してしまっている状況に接して、何とかその主体性を取り戻せるような手続を考えられないか、と悩みつつ、昼も夜も日米の文献を読んで、夜中に構内の猫と語ることが息抜きといった日々も日常となる頃、何となく吹っ切れて、論文の構想(妄想)が生まれるようになりました。その頃、指導教授には「研究は楽しくやりなさい」と繰り返し言われ、当時はそれどころではなかったのですが、今思えばこれは真髄でした。研究者であった父に、「努力する者ほど迷う」と言われたことも、支えになりました。助手生活で学んだのは、客観的な根拠がなくとも自分を励まし進んでいく楽天性ということでしょうか。
学部時代は女子は1割でしたが、性差を気にすることはありませんでした。むしろ助手になってから、女の学部助手は数十年ぶりというプレッシャーとか、就職で不利になるという予言(?)、研究会等で指導が甘いのではないかという思い込み、等々意識せざるを得なくなりました。若かったこともあり、「女性初の」という枕詞に過剰に緊張しつつ、伝統的な性役割にも応えなければといった八方美人的な鎧も着ていたように思います。
その後、米国に遊学して、どのロースクールでも盛んなジェンダー教育・研究に接し、上記のような過剰反応や鎧は普遍的であることを知り、また、自分は中立的と思っていても実は男性的視点と指摘されて驚くなど初歩的経験をしました。また、研究生活で落ち込んだり悩んだりする仕方が女性の友人とは(国境を超えて)共通であることが分かって、初めてそれまでの孤独感に気づいたりもしました。性差を含めて生身の人間性が研究生活の前提となることを知る良い機会だったのですが、実は、この原稿を書くまで忘れていたことを自白せねばなりません。これを機会に初心に戻り、今度はこのような情報を提供できるように務めなければと思っています。