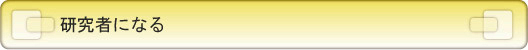新山陽子(農学研究科・教授)

刺激的な研究の世界
研究者になる!がテーマであるが、ふりかえってみると研究者としての自分がもてるようになったのはかなり遅かったように思う。今もまだ進歩(だとよいが)の途上である。
私は1970年に京大農学部に入学し、応用生物学をやりたいと思っていたが、途中で社会科学に興味をもち農業経済学に転学科した。きっかけは友人に誘われて経済学部のサブゼミに加わったことであり、学部の壁が低い京大ならではのことだったかも知れない。チューター役の院生の人の手ほどきを受けながら経済学の原典を読んだことが、研究への関心につながったように思う。
大学院時代のゼミは厳しく、ただただ、もがき苦しんだ。農業経営学の分野に進んだが、一般経営学や農業経営学の学説を徹底して見直すことがゼミの課題だった。最初は経営経済学というものの目線にどうしても得心がいかず、これだけやってもまだわからないのか!と指導教官に怒鳴られたこともある。それでやっと川を飛び越せたくらいで、この頃はまるで霧に包まれたように研究の方向性が見通せなかった。でも、このなかで今の思考の基礎ができたように感じている。進路についても、オーバードクターが大勢いた時代で、私は研究室最長の5年間をODで過ごし、研究室の助手に採用されてようやく終止符を打った。
この時期を乗り越えることができたのは、何よりも研究室の仲間の存在があったからだと思う。今でも彼らは大切な存在であり、何かにつけてやりとりしている。さらに、これが最大の要素だったかも知れないが、フィールドが、おもしろかったからだったと思う。博士課程になって和牛の新興産地の構造分析を始めた。鹿児島、岐阜、青森などへ頻繁に通い、多くの人たちに現場のことを教えていただいた。精通するのに10年近くかかったが、小さな単行本にまとめることができた。また、指導教官のけっして甘やかさない容赦のない厳しい指導があったことも、あきらめずにやれた一因かも知れない。長いODのすえに2年続けて病気をしたとき、体を張ってやっていないと叱られたことを今でも思い出す。
しかし、職についても研究上の確たるものはなかなかつかめなかった。1989年に講師になり、94年に助教授になったが、長く続けた肉牛経営の企業形態の研究を2冊目の単行本にまとめた頃(1996年)にようやくにして研究の足場がしっかりした。
その後は、研究分野に関連する大きな社会問題の波を受け、それに対応しながら研究を進めるようになった。厳しいことではあったが、現実との緊張感のなかで新たな理論にも出会い、多くの人たちとの関係ができたのがうれしい。
その最初は、1991年の牛肉輸入自由化である。これをきっかけに、アメリカや欧州に調査を広げ比較研究をするようになった。研究の第一歩は比較にあるというが、まさしくその通りに視野が大きく広がった。また、理論枠組みのオリジナリティがだせていないことが一番苦しいことであったが、それもフードシステム論という新しい分野ができ、新しい学会が創設されたことをきっかけに進展した。新しい枠組みをもとに『牛肉のフードシステム−欧米と日本の比較分析−』(2001年)をまとめたのはしんどかったが、かなりわくわくした。
そしてこの直後にまた大きな変化が起こった。その年の秋、国内でBSE(牛海綿状脳症)が発見され国を揺るがす事態になったのはまだ記憶に新しいできごとであろう。ちょうど欧州のBSE対策をみていたことから、嵐のような食品安全行政改革の渦中に放り込まれてしまった。新しい政策や法律の立案のプロセスをそのただなかでつぶさにみることができたのは、社会科学の研究者としては得難い経験であった。その前後で世界がすっかり変わってしまったようにさえ思う。まったく新たな勉強をし、行政や事業者の方々、異分野の研究者たちと仕事をするようになった。
食品安全研究のために学際的な研究会をつくった。食品衛生、獣医衛生、公衆衛生、法学、心理学、機械工学、われわれ農業経済学の分野のものが集まっている。それはとても緊張感にみちて刺激的である。また、この春には、卒業生の方と食品企業数社から寄附をいただき、寄附講座「食と農の安全・倫理論」を開設した。二分野一講座が一緒になって同名のプロジェクト研究をはじめている。
このなかから新しいテーマがたくさんでてきた。消費者の食品選択行動やリスク認知を把握するため、無謀をかえりみず認知心理学をも取り入れているし、コミュニケーション手法の開発、食品衛生のプロフェッションの確立と職業倫理の探求などもはじめようとしている。社会的に喫緊であり、研究者にとってもおもしろい課題が山積している。