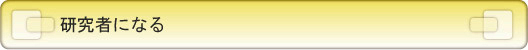押川文子(地域研究統合情報センター・教授)

大学の外にも研究職はある
正直なところ「研究者になる!」という題名の原稿、私には書きにくい。振り返ってみると私の過去は幸運の連続で、「研究者になる」ために刻苦勉励してきたというものではないし、現在も「研究者になっている」のか否か、心もとない。ただ、小さな大学の出身で、最初の就職から昨年春に京都大学に移るまで一度も大学に在籍したことがなく、とくに最初の20年近くを文部科学省の管轄外の機関で働いた私のケースは、こんな例外もあるのかという意味で何がしかの参考になるかもしれない。
私が大学に入学したのは1969年春、2年間のインド留学をはさんで修士課程を修了したのが1977年までの時期を東京の小さな国立女子大学史学科の学生として過ごした。インドへの関心は、大学に入る前からあった。幸運にも、若い私が勝手に夢想し選んだインドという対象はまさに「当たり」で、知るほどに底なしに面白く難しくなっていくテーマだっが、当時の私は研究者になろうとも、またなれるとも思ってはいなかった。学外の研究会などには参加していたものの、当時のお茶の水女子大学にはインド史専門の教員はおられず「学界」は遠かったし、史学科など文系学科の教員はほぼすべて東大出身の男性教員で研究職へのルートも見えなかった。大学の教員ポストの多くがまだ公募になっていなかった当時、出身大学は研究職につくうえで現在よりもさらに重い意味をもっていたように思う。優秀な先輩たちのなかには大学院で他大学に移るケースもあったが、不勉強のうえに学部卒業前に結婚した私は、ままごとのような家事を結構楽しみながら、中学校か高校の社会科教員になろうか、と漠然と将来を考えていたように思う。
その教職試験をうける前の最後の言い訳として受験したインド政府留学生試験の補欠合格の電話が入ったのは、修士2年目の7月だった。2週間後にネルー大学に出頭できれば合格にするという。その一瞬、何か封印していたものが頭のなかではじけたような記憶がある。夫にも相談せず行きますと即答し、2年間デリーで、学生としてはじめて真面目に勉強することになった。ただ、帰国してみれば、状況は以前とまったく変わらない。インド留学など一般職では何の役にもたたず、むしろ2歳年齢を加えた分だけ就職活動は不利である。職種はともかく生活のために就職する必要があり、年齢制限ぎりぎりで受験したアジア経済研究所に採用されたのは、まさに幸運としかいいようのないことだった。
アジア経済研究所、通称アジ研は、通産省(当時)管轄の特殊法人で、アジア、アフリカ、ラテンアメリカなどを対象とする研究機関である。アジ研の特色のひとつは、「研究職」を特別視しないという点にあった。研究職の採用も当時は原則として学部卒、賃金体系も事務系と同じだった。出勤管理はタイムカード制、子育て中の職員は有給休暇を1時間単位でとることも多く、3月には給与カットという例もあった。労働組合が機能していた点も特色である。特殊法人という枠内ではあれ労働条件は労使の交渉マターであり、育児時間などはこの交渉を経て、少しずつ期間延長が獲得されていた。男性の育児時間や育児休暇の導入も早かった。再生産にかかわる権利の男性への保証という点では、1970年代から80年代にかけてアジ研は日本でももっとも先進的な職場の一つだっただろう。私も入所3年目に息子を出産し、毎日、時間を気にしながら保育園と職場と自宅の間を回りながら暮らしたが、子育てを理由に職場で非難されたり苦労したという記憶は不思議なほどない。
研究面では優秀な先輩たちに恵まれた職場だった半面、当時、こうした研究職の特殊性(特権)を認めない就労条件を窮屈に感じ、大学教員の自由を羨ましく思ったこともある。しかし、今振り返ってみると、むしろプラス面が大きかったように思う。研究という仕事には限度がない。一見自由に見えて、研究以外の要素をいかに自己処理して無限に働くかが問われ、その結果を評価される。評価が叫ばれる昨今の大学では、よりその傾向が強い。当然、現在の日本社会では男性が有利であり、「仕事さえできれば男女は関係ない」という常套句は、時として女性研究者にはもっとも厳しい条件となる。アジ研での経験から私が学んだことは、研究という無限の営為と生活者としての個人を両立させるためには、個人としての努力だけでなく、研究職であるからこそ意図的にその無限性に歯止めをかける職場環境が必要だということ、それは男女ともに平等に保証すべきこと、という単純なことだった。
女性研究者支援が、女性の自己処理能力への補助にとどまるのではなく、育児中の男性教員・事務職員への支援、そして研究者の働き方の変化につながるものであることを期待している。その方向がない限り、女性が「研究者になる!」ことは、いつまでたっても何か例外的なこと、特筆すべきことにとどまるのではないだろうか。